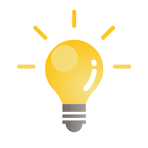Contents
なぜ今、部活動の外部化が求められているのか
教育現場では今、「部活動のあり方」そのものが見直されています。少子化が進む中で教員数が減少し、過重労働が問題視されていることが背景にあります。そうした中で、文部科学省も提唱しているのが、部活動の「外部化」や「地域移行」です。
放課後や休日の指導を外部の専門家や地域人材に委ねることで、教員の負担を軽減し、教育の本質に専念できるようにする狙いがあります。
しかし現場では、理想と現実のギャップが表面化しています。「外部に任せたくても、指導者がいない」という問題です。特に技術や安全管理が必要な競技は、単なる補助では成り立たない場面も多く、指導者不足は深刻です。
外部化のメリットと課題の二面性
教員の働き方改革としての意義
部活動の外部化が推進される背景には、教員の労働環境の改善という大きな目的があります。特に、長時間勤務や休日の練習、試合帯同などが常態化していた教員にとって、部活動から解放されることで授業準備や生徒指導により集中できる環境が整います。
また、専門知識を持つ外部指導者による練習は、生徒にとっても技術向上や視野を広げるチャンスとなるため、教員・生徒双方にメリットがあるといえるでしょう。
指導の質・責任の所在の不透明さ
一方で、外部指導者の配置が進まない、あるいは安定しないという現実も見逃せません。部活動は「教育活動」としての側面が強く、単に競技指導ができるだけではなく、生徒との関わり方や安全管理、チーム運営といった面も求められます。
誰が責任を持つのかが明確でない、また、外部指導者の入れ替わりが激しいといったケースでは、指導の継続性や信頼性が保たれず、生徒のモチベーション低下にもつながる恐れがあります。
深刻化する指導者不足の4つの要因
報酬・待遇の問題
多くの自治体では、外部指導者に対する報酬が低く、交通費程度、あるいは無償ボランティアで対応している例も見られます。これでは人材確保が難しく、優秀な人材の定着にもつながりません。
指導人材の高齢化と世代交代の遅れ
これまで地域で指導を担ってきたのは、定年退職した教員やベテランの地域住民が中心でしたが、高齢化により指導を継続するのが難しい状況も増えています。若い世代への引き継ぎや育成が進んでいないのが実情です。
部活動の多様化と専門性の不足
体育会系、文化部系だけでなくeスポーツなどの活動も含め、部活動の選択肢は年々多様化しています。その分、それぞれに対応できる専門的指導者を確保する必要があります。
責任問題・事故リスクへの不安
部活動では、ケガや熱中症といった事故の発生リスクもあるため、外部指導者が万一の責任を問われることへの不安から、指導を敬遠するケースもあります。保険制度の整備や契約内容の明確化が必要です
ソフトテニス部の現場で見られる課題例

地域による指導者格差
都市部では指導経験者やスクールも多く、外部化への移行が比較的スムーズに進みますが、地方ではそもそも人材が不足しており、週に1回も練習ができない学校すら存在します。
技術継承の難しさと競技力低下
指導者が毎年変わる、もしくは未経験者が形だけで担当している場合、競技としての水準が維持できず、生徒の目標達成にも悪影響が出ます。ソフトテニスでは、フォーム矯正・ポジショニング・ペア戦術といった要素が重要であり、継続的な指導が求められます。
乗り切るための7つの現実的対策
指導者不足という現実に対しては、1つの解決策に頼るのではなく、多角的なアプローチが求められます。ここでは教育現場と地域が連携しながら実行可能な7つの施策を紹介します。
地域クラブや総合型スポーツクラブとの連携
各地域に存在する総合型地域スポーツクラブやNPO、自治体主導のスポーツ推進団体と連携することで、定期的な指導者派遣が可能になります。ソフトテニスでは地域のクラブチームと連携し、土日だけコーチを派遣するといった形も有効です。
引退教員・OB・OGの再活用
かつて教員や部活顧問として指導に関わっていた人材、または卒業生(OG・OB)など、競技経験と教育的配慮を両立できる人材のネットワークを再構築することも重要です。例えばソフトテニス部出身者が週末のみ指導に戻るといった例も増えています。
指導者育成支援と研修の充実
部活動指導員の研修制度を整備し、教員でなくても指導可能なスキルと倫理教育を提供することで、人材の裾野を広げることができます。簡易的な認定制度や地域限定ライセンスの導入も検討されつつあります。
ICT・オンラインツールの併用

リモート会議ツールや動画解析アプリ、トレーニング管理アプリなどを活用すれば、常駐型の指導者がいなくても、オンラインで助言・指導を受ける体制が可能です。ソフトテニスのような技術系競技では、フォーム解析や戦術解説にも有効です。
部活動支援アプリ・マッチングサービスの活用(Hittingなど)
近年、スポーツ指導者と学校・個人をつなぐマッチングサービスも登場しています。たとえば「Hitting」のようなサービスでは、ソフトテニスに特化した指導者とプレイヤーをつなぐ仕組みが整っており、必要な時だけ指導者を呼ぶという柔軟な対応が可能になります。
自治体主導の人材バンク整備
地域内で指導可能な人材を一元管理する「スポーツ人材バンク」の整備は、自治体単位で進めるべき課題です。特に地方では競技別・レベル別に指導可能な人材を把握・登録し、各学校のニーズに応じて派遣するシステムが必要です。
学校と地域のハイブリッド運営体制
外部化を「完全移行型」と捉えるのではなく、学校教員と外部指導者が協力するハイブリッド型運営を基本とすれば、指導の一貫性を保ちつつ、業務負担も軽減できます。ソフトテニス部では、「技術指導は外部、生活指導や大会引率は教員」といった役割分担が効果的です。(私も現在外部指導員といして活動していますが、役割分担が主な方法となています。)
保護者と地域の理解を得るには?
部活動の外部化を進めるうえで欠かせないのが、保護者や地域住民の理解と協力です。特に中高生の成長期に関わる活動である以上、家庭や地域と学校がしっかり連携することが求められます。
情報共有・説明会の工夫

外部化の目的や運用体制、指導者の安全対策、費用負担の有無などについて、定期的な保護者説明会を実施することが信頼形成につながります。特に、誰が指導するのか、どんな指導が行われるのか、責任の所在はどこにあるのかといった点を明確にしておくことが重要です。
また、紙ベースだけでなくLINEオープンチャットや学校のウェブサイトを活用して、随時情報を共有できる仕組みを構築すれば、双方向の理解と協力を得やすくなります。
成果の「見える化」とフィードバック
保護者が部活動の成果を感じ取れるように、定期的な成果報告や練習動画の共有、試合結果の通知などを行いましょう。特にソフトテニスのような競技では、技術の向上が目に見えにくいことも多いため、練習の進捗や指導の内容を見える化することで安心感につながります。
また、保護者や生徒からのフィードバックを定期的に受け取り、柔軟に運営方針を調整する姿勢も大切です。一方通行ではなく、「聞く」体制をつくることで、外部指導体制への信頼度が高まります。
まとめ
まとめ:部活動を持続可能にするために今できること
部活動の外部化は、教員の負担軽減と教育の質向上を目指す重要な取り組みです。しかし、それに伴って深刻化する指導者不足に対しては、多様な人材の活用、ICTの導入、地域との連携といった現実的かつ柔軟な対応が不可欠です。
ソフトテニス部のような専門的指導を要する部活においても、Hittingのようなマッチングサービスや地域人材の知恵と力を借りることで、新しい部活動のカタチが見えてきます。
すべての生徒が安心して学び、成長できる場を守るために、教育現場・地域社会・保護者が一体となって、新しい時代の部活動運営を築いていきましょう。
お申込み・お問い合わせはこちらから
TEL:070-5599-7110
公式LINEはこちらから