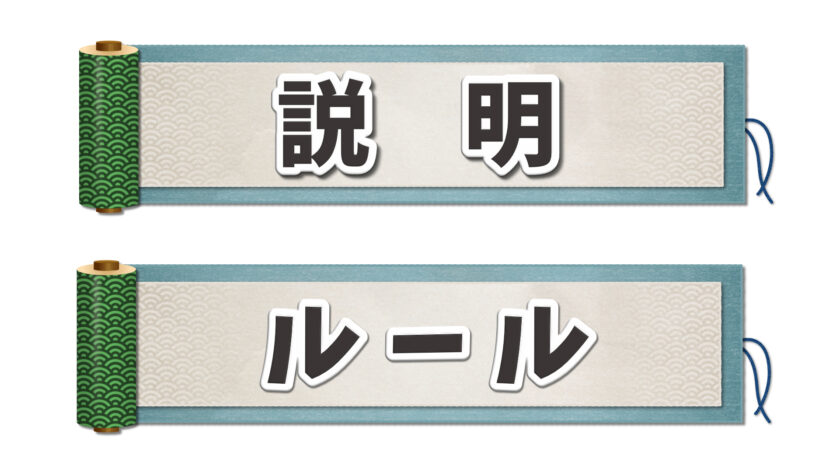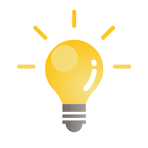Contents
だんだんと気温が高くなる今日この頃、さまざまなスポーツで暑さに対応したルールが導入され始めています。
今回は、ソフトテニスにおける「ヒートルール」について解説していきます!
意外と誤解している人も多いのではないでしょうか?
ソフトテニスハンドブックに基づくヒートルール
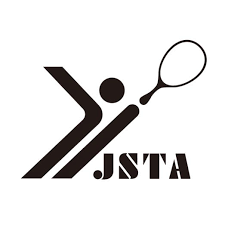
競技規則 第46条
会場での気温(乾球温度)が35℃以上となり、ファイナルゲームとなった場合、ファイナルゲームに入る前に、3分間のテニスコート内の日傘による日陰(アンパイヤ―の目が届く範囲)での休憩を許可する。
なお、3分間については、第17条(2)(※)の1分間を含むものとする
(1)団体戦の場合、1分間は助言を受けることができるが、残り2分間については助言を受けることができない。
(2)気温の測定にあたっては、大会責任者等がコートサイドの風通しの良い場所を決定し、1時間~2時間の感覚で実施する。
(3)会場で正確な気温が図れない場合は、環境省が提供する「暑さ指数(WBGT)」予測値等電子情報サービス」の会場地に最も近い地点でのWBGT値を参考とする。
※第17条(2)について
マッチ開始から終了まで連続的にプレーし、次の行為をしてはならない。ただし、サイドチェンジおよびファイナルゲームに入る場合は、ポイントの終了から1分以内に次のポイントを開始する態勢に入るものとする。(レッツプレー)
ア.相手がレシーブの構えをしているのにサービスをせず、又は相手方がサービスをしようとしているのにレシーブの構えをしないこと。
イ.故意にマッチを長びかせる行為をすること。
ウ.マッチの進行に支障となる状態でパートナー同士の打ち合わせをしたり、又は休息をとったりすること。
エ.ゲーム終了後次のゲームに移る構えをしないこと。
オ.ファイナルゲーム内のサイドのチェンジの場合に休息すること。
カ.ラケットを修理すること。
以上が第17条(2)に該当
詳しい規則はソフトテニスハンドブックをチェック
ヒートルールに関する詳しい内容はこちら
勘違いされやすいヒートルール
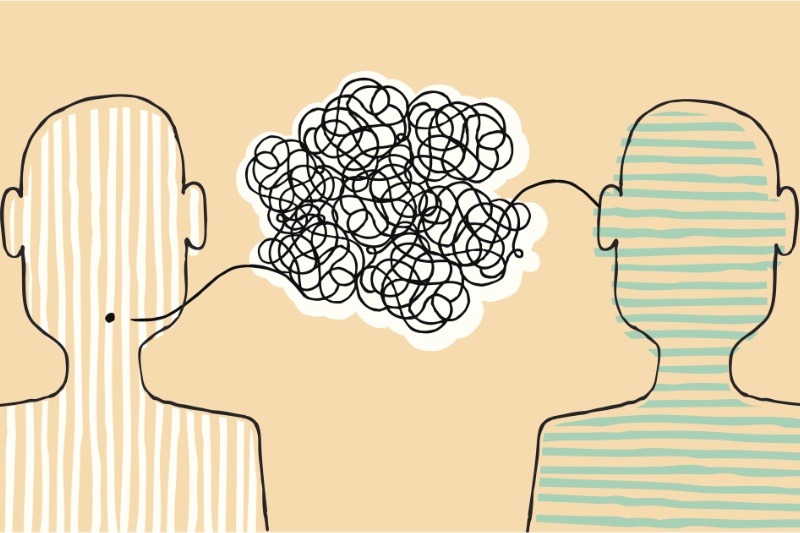
よく大会開会式等で、「ヒートルール適応するため、チェンジサービス時も水分補給ありとします。」など聞いたことがある方も少なくないと思います。
しかし、これは各大会独自のルールであるため公式にヒートルールとは言われません。
審判員試験時にテストで問われる可能性もあるため要チェックです。(ソフトテニスハンドブック購入はこちら)
今後の展望
今後のヒートルールはさらに変容していくと考えられます。
AI・IoTによるリアルタイム環境モニタリング
WBGT値のリアルタイム把握、さらには選手の心拍数や体温を測定し、選手の健康状態の維持を促進。
一定基準を超えると試合が中断、強制的な休憩が導入されるなどの仕組みが普及するかもしれません。
クールダウン施設設置の義務化
選手側の規定のみならず大会側にも、施設の設置を求められる世になると考えます。
大会開催側も協力して安全な環境づくりが求められるでしょう。
まとめ
近年の猛暑に伴い、ソフトテニス界でも「ヒートルール」への関心が高まっています。この記事では、まずソフトテニスハンドブックに基づいた公式のヒートルールを紹介しました。特に注目すべきは、気温が35℃以上となった際に導入される3分間の休憩ルールや、その中での助言の可否など、細かな規定が設けられている点です。
また、「ヒートルール=給水OK」などの独自ルールからくる誤認識も多くあります。実際には、各大会が独自に設ける暑熱対策と公式ルールは区別されており、審判員試験でも出題される項目となっております。試験を受ける際には区別をはっきりできるようにしましょう。正しい理解はソフトテニスハンドブックを正しく読み解く姿勢が大切です。
さらに、将来の展望として、AI・IoTを活用したリアルタイムの環境モニタリングや、クールダウン設備の義務化など、技術とルールの融合による安全対策の強化が進む可能性も考察しました。選手の安全と競技の質の両立を図るために、大会運営者と選手が協力していくことが重要です。
ヒートルールは「今あるルールを守る」だけでなく、より良い環境づくりの一歩でもあります。この記事を通して、少しでも理解が深まり、より安全なソフトテニス環境の構築に繋がることを願っています。
お申込み・お問い合わせはこちらから
TEL:070-5599-7110
公式LINEはこちらから